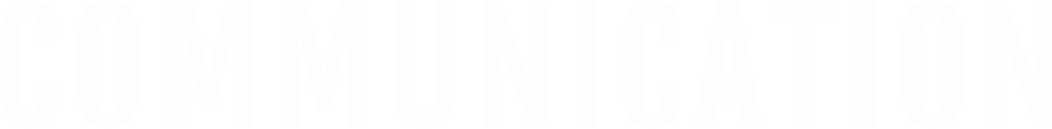ぷれすスタッフによる不定期連載コラム
なんでも書いていいって言ったじゃないか! 第10回

ギョーム氏との再会
三輪しののい
ギョーム氏と再会した。実に21年ぶりだった。何しろもうお目にかかることはないだろうと思っていたので、会えると知ったときは欣喜雀躍した。
とはいえ、会うべきか会わざるべきか逡巡したのも事実だった。再会というのは美しい記憶を上書きしてしまい、場合によってはすべてを台無しにしてしまう可能性もあるからだ。
ギョーム氏は白いシャツに、褐色の影がかかったえんじ色のネクタイをしている。黒のジャケットをはおり、黒いソフト帽をかぶって口ひげを生やして首を傾げ、少し顎を突き出している。そのせいか、まなざしは優しくあるものの、やや人を見下しているようにも見える。軽くあげた左手の指先にはタバコ。なんだか不遜な感じを与えもする。
けれども21年前に彼と会ったとき、醸し出す雰囲気に圧倒されて僕はその場に立ち尽くしてしまった。
「ジャズだ!」と思った。
背にした薄暗い雰囲気の赤茶けた壁といい、タバコの傾き具合といい、なぜだか知らないけれど僕がイメージするジャズの鳴る空間が立ち上がり、いつしか耳に無音の音色があった。
出会いの場所は京都だった。近県にある大学に籍を置いていた僕は、講義をサボりふらりと各駅電車に乗って時間をかけて京都まで来た。
銀閣寺の近くで湯豆腐を食べ、そのあと「哲学の道」を散歩することにした。季節は秋で穏やかな陽光が色づいた葉を慈しむように撫でていた。まだ寒くないし時間もたっぷりある。当時はそんな風にして、地図も持たずに知らない街をあてどなく歩いたものだ。
南禅寺にたどり着き、さらに歩いてみると大きな鳥居の横に美術館の案内が目に入った。どうして美術館になんて入ろうと考えたのか今となっては思い出せない。
はっきり言って美術についての知識はゼロだったし、自分の意思で美術館に足を運んだ記憶もなかった。だから「オランジュリー美術館展」というのが、どういうものなのかさっぱりわからなかった。
そう、お気づきのとおりギョーム氏とは豪華な額縁の中で生き続ける20世紀初頭はエコール・ド・パリの画商、ポール・ギョームのことである。描いたのはイタリアの画家、アメデオ・モディリアーニ。
何もわからないままチケットを買って緊張しながら中に入ると、思いのほか人が多くてびっくりした。セザンヌ、ルノワール、ピカソと僕でも耳にしたことのある巨匠の作品が続く。
淡々と見て回っていただけに、ギョーム氏を前にしたときの衝撃がいかほどだったかおわかりになろう。そして、いきなりジャズとリンクしたものだからびっくりしてしまったわけである。
左上にはPAUL GUILLAUMEと黒い文字が、左下にはふきだしのような曲線の中にNOVO PILOTAと白い文字があり、これまで目にした絵とは違った趣があった。右上にも何やら文字らしきものがあり、右下にあるMODIGLIANIというサインの下には吉報の鉤十字と、うっすらとだが大きく1915と制作年も記されている。
シックな色使い、油彩のでこぼことした質感、ヒビの数々など、角度を変えて隅から隅まで鑑賞した。
いったいこの絵の魅力とはなんだろう?
誰も寄せ付けない構えで、その105×75cmの絵をしげしげと見つめた。
数か月のあいだ記念に買い求めた図録を眺めていたが、やはりギョーム氏は特別でページをカットして額装することにした。以来、色あせながらも部屋には氏の分身がいるわけである。
再会のために用意された地は横浜だった。ギョーム氏がパリへ戻る日も近づいた冬のある朝、上書きの懸念を振り払い、コートの下に黒いジャケットをはおって美術館へと足を運んだ。
チケット売り場は列をなし、中に入ると京都のときと同じように混んでいた。静かなフロアには21年前に見た絵の数々がずらりと並んでいる。どこに氏がいるのかドキドキしながら一点一点じっくりと鑑賞した。星の数ほどの視線を浴びて今に残る本物の絵は、言うまでもなく図録の印刷とはまったく異なる。図録に慣れてしまった目が覚醒していく。会場を進むにつれて色彩による高揚感を覚える。
当たり前のことだが21年ぶりということは21歳トシをとったということである。その間にいくつかの出会いと別れがあり、トラブルと克服があり、暴食とダイエットがあった。生きる意味とか答えばかり求めて観念の世界に閉じこもっていた僕も、傷を負いつつ社会人としてなんとかここまでやってこれた。そして、こつこつと買い集めたジャズのCDが何百枚にもなってラックに収まっている。
「再会できるとは夢のようです」
声に出さず挨拶した。目の前に立つギョーム氏は昔と同じポーズで迎えてくれた。
「21年間、あなたの分身が僕を見守ってくれました。僕もあなたのことを毎日見ていました。NOVO PILOTA(新しき水先案内人)としてあなたは確かに僕を導いてくれました。ジャズをあのとき感じたのですが、今日は少し違うようです。きっと一緒にCDを聞きすぎたのでしょう」
照明が近すぎるため反射して右上がよく見えない。そこにはダビデの星や、STELLA MARIS(海の星。聖母マリアの意)という文字があるのに。
立ち止まっては去っていく人々を意に介さず、ずっと氏に語りかけた。あまりに長くいるものだから、後ろにいた学芸員に怪訝そうにじろじろ見られたほどだ。
「あなたに教わったことがあります」
うまい具合に人がはけたとき、僕は真正面に立って切り出した。
「それは、絵を見るときに言語を忘れることです。みんな絵を見ると同時にその横にある解説文を読んでいます。解説文を読みに来ているみたいです。それを読んでその場を去る人も多いのですから」
美術館に響く人々のざわめきが消え去っていく。
「額縁の中にある世界に引き付けられたとき、その世界に満ちている言語化されないメッセージをありのままに受け取ること。そして自分の奥底から何かを引っ張り出したり見出したり、共鳴に驚いたりすること。そのプロセスや姿勢こそが、まなざしに生命を宿すのですよね」
「答えがあるわけではない。他人の解説や解釈をなぞるのは、あくまで自分を相対化する試みの一つに過ぎないし、そのためには前提として自分というものがなくてはいけない。自分を見つめなくてはいけない。京都であなたと会って気づいたのはそのことです」
年月のせいか、ギョーム氏の首の横に白い線が浮き出ていた。分身を見続けてきた僕はちゃんとそのことに気づいた。やはり氏にも年齢はあるのだ。
「僕はこれからも直面するすべての出来事に対して、自分なりの感じ方や捉え方を大事にして、そこから何かを学びとっていきます」
本物の絵と真に向き合ったとき、やがてその世界は額縁を超える広がりを持つ。絵の中の世界は現実の世界につながり、それを捉える視野も広がっている。
僕はギョーム氏の体験を通じて視界が晴れたのだ。解説文という副次的なものに目を奪われるようでは、いつまでたっても本物を見ることはできない。
パラフレーズするならば、人生を誰かの解釈に任せてはいけないということである。
美術館を出ると海からの風にマフラーがなびいた。昼の日差しを浴びながら少し遠回りして、みなとみらい駅へと向かう。「新しき水先案内人」はこれからも僕に何かしらのヒントを与えてくれるに違いない。
記憶の上書きを恐れていた僕だったが、ギョーム氏は記憶の核心を残したまま、膨らみをそこに付け加えてくれた。過去と今を混ぜ合わせた彩りによって世界を塗り替え、平板な日常に新たなスタートラインを引いてくれた。
ありがとう、ギョーム氏。また会えたとき、僕は同じまなざしであなたを見つめられるように、真摯に生きていきます。
〈出版の窓〉
モディリアーニほど表記が定まらない偉人も珍しいのではないでしょうか?
国立国会図書館サーチで調べてみたところ、古くはモヂリアニ、モヂリヤニ、モヂリアニイなど、時代を感じる揺れが見られますが、旧仮名遣いで外来語の表記指針もなかった時代なので、特段珍しいとは言えません。
しかし21世紀の今ですら、モディリアーニとモディリアニが拮抗しているような状態が続いています。平成3(1991)年に内閣告示・内閣訓令として「外来語表記」の用法が通知されていますが、あくまで目安・よりどころという位置付け。用例集として人名も挙げられているものの、残念ながら「モ」の欄にその名は取り上げられていません。『共同通信 記者ハンドブック』では外国人名表記例として、モディリアニを採用しています〈注:手元で確認できる平成17(2005)年第10版以降のみ〉。一方、図録の表記は平成10(1998)年のものも令和元(2019)年のものもモディリアーニとなっています。
動画でイタリア人の発音を聞いてみたところ、やはり音引きありのモディリアーニが原音に近いと感じます。ちなみに、この表記が最初に見られるのは昭和23(1948)年のよう。見る者の心を揺さぶる彼の絵と同じように、その表記も揺れ続けるのでしょうか?
追記 ポール・ギョームの表記も平成の図録ではギョーム、令和の図録ではギヨームと揺れています。本稿では21年前から親しみ続けているギョームで通しました。
《著者プロフィール》
三輪しののい
1976年生まれ。神奈川県出身。