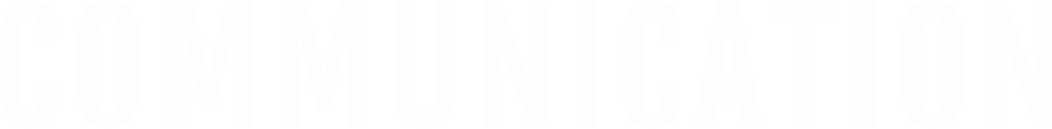ぷれすスタッフによる不定期連載コラム
なんでも書いていいって言ったじゃないか! 第22回

新刊とは「教材」である
三輪しののい
校正者の楽しみといえば、やはり担当したゲラが本や雑誌として完成を見ることである。
制作側の手の中であたためられていたものが、美しい装いでお披露目され、読者のもとへ羽ばたいていく。
リアル店舗でもウェブストアでも、担当したタイトルが並べば、頑張った甲斐があったというものだ。
しかし、そうした達成の喜びとは別に、校正者の胸を躍らすことがある。
ゲラに入れた指摘が、著者や編集者にどのように判断され処理されたのか、本の完成によって確かめられるという喜びである。
書籍を例にとるが、校正に出すゲラをつくるまでに、編集者やライターが著者とともに原稿をみがいて、ある程度のクオリティにまで仕上げている。
とはいえ、校正者という最初の読者(第三者)からしてみると、ひっかかりを覚えたり、わかりづらいと感じたりするところが出てくるものだ。
そのため、初校では、誤植や表記統一、事実関係の指摘以外に、文章表現などに関する疑問出しが入るのが常である。
特に実用書系は、文芸作品と異なり、わかりやすい文章であることが重要なので、編集者から「気になったところは遠慮なく疑問出しを」というリクエストも多い。
もっとも、文章をまるまる書き直したり書き足したりはやりすぎで、あくまで現状の文を生かしたうえで、前後を入れ替える、まわりくどい言い回しを簡潔な表現にするといったところまでである。
もし、センテンスやパラグラフ単位で、前後関係に矛盾や違和感があるようなら、2~3行でその旨を伝えておけばよい。
では実際のところ、これら疑問出しはどのように解決されているのか?
答えは、まさに種々雑多である。
そのまま採用されるところもあれば、書き直されたりカットされたりするところもある。もちろん原文ママとしてスルーされることも多い。
判断基準は本によってばらばらだ。
採用されている箇所が多ければ嬉しく思うし、文が練り直されていれば、著者の力量や粘り強さを感じる。ほとんどがスルーされてしまうと、やはり残念な気持ちになる。とりわけ「これは著者へのナイスパスだ」などと、得意になっていたところがノータッチだった場合はがっかりするものだ。
しかし、ただ落ち込んでいるだけではもったいない。
「あの疑問出しは自己本位だったかもしれない」
「読み込みが足りず、的外れだったのかもしれない」
このように振り返りの場とすることで、人知れず技をみがいていく。
疑問出しというのは共通した答えがあるわけではないため、場数を踏み、勘所をつかんでいくしかないのだ。
そう考えると、新刊というのは担当校正者にとって、極私的な「教材」であるともいえる。
全部をおさらいするのは難しいが、経験を積むほど教材の数は増えていき、学びのチャンスも広がっていく。
皆に読まれるための本づくりに携わりながら、一方で自分のための教材を準備しているという二面性こそ、この仕事にゴールがないことを表してはいないか。
だから、校正者は次のゲラを求める。
何十冊、何百冊と、飽きることなく文字との格闘を挑み続ける。
〈出版の窓〉
本にしたときと同じレイアウトで文字や図版を組んだものがゲラです。初校が出ると、なりふり構わずといった感じで、刊行へまっしぐらに進みます。2回、3回と校正を重ねて編集側の手を離れると、舞台はいよいよ印刷・製本工場へ。何千冊といった初版分の新刊が誕生するわけです。
その間、約2カ月。
もちろん、ボリュームや刊行スケジュールによって異なりますが、ゲラにあれこれと指摘を入れていた校正の身からすると、「もうできたの!?」とびっくりしてしまうことも。
しかし、本はそう簡単につくれるものではありません。企画会議があり、執筆期間があり、リライトや原稿整理といった時間の蓄積があるわけで、校正者は刊行までの道のりにおける最後の部分を手伝っているにすぎないのです。
ゲラに辿り着く前の「根っこの部分」があることを肝に銘じて、謙虚な気持ちで指摘を入れないといけませんね。
《著者プロフィール》
三輪しののい
1976年生まれ。神奈川県出身。