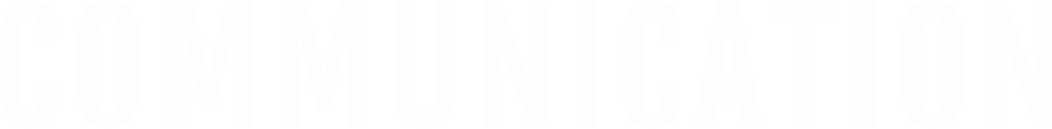ぷれすスタッフによる不定期連載コラム
なんでも書いていいって言ったじゃないか! 第6回
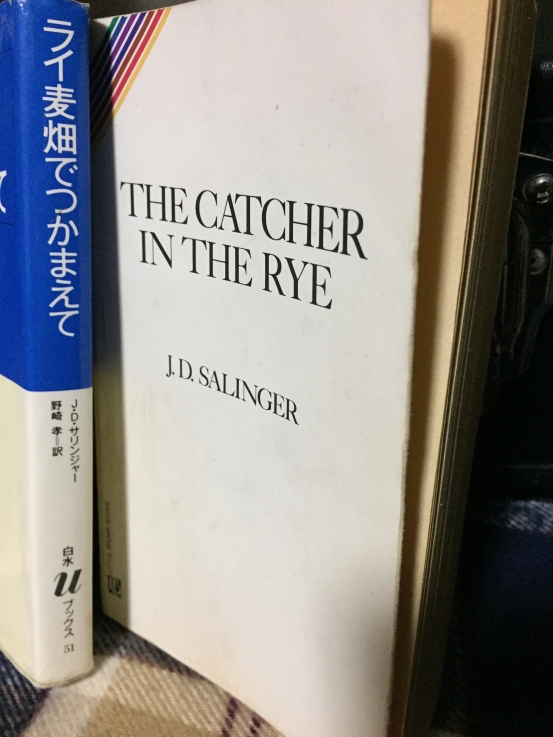
イノセンスから遠く離れて
三輪しののい
神奈川県のとある街にかれこれ20年近く住んでいる。会社まで1時間ちょっとかかり、そのうち40分近くを電車の中で過ごすのだが、行きも帰りも座れるので本を読んだり眠ったりして、通勤の苦しみというものをさして感じることはなかった。
ところがここ数年、駅周辺の宅地開発が進み、ショッピングモールができてすごい賑わいを見せるようになった。最初は便利になって良かったなどと喜んでいたのだが、人口増加に伴い電車が込むようになってしまった。帰りは今までどおり変わらないものの、行きの電車が時として座れないのである。
オフピーク時のローカルめいた路線(途中メトロに乗り入れる)で、始発駅から2駅ということもあり、どの車両もぽつぽつとしか乗客がいなかったのだが、今はぽつぽつとしか席が空いていない。雨でダイヤが乱れたりすると席は完全に埋まり、車内が空くメトロの駅まで30分は立つことになる。
そんなわけで、利用する駅を始発よりの駅に変えることにした。
自宅はその2駅の中間に位置しており、休みの日などはこちらの駅を利用することもあった。急行が停まらないのでやや不便な面もあるが、確実に座れるしホームにエアコンつきの待合室があるので快適である。
駅まではてくてくと歩いていき、しばらくすると小学校の裏に出る。その横を通ると、音楽室から児童たちの歌声と先生のピアノの伴奏が聞こえてきて、これがなかなかいい。
思えば僕は一貫して音楽の成績だけは良かった。小学校3年生くらいまでピアノ教室に通っていたので、苦手意識を持たず授業を受けられたのが良かったのかもしれない。ほとんど練習せずまったく上達しなかったが、楽器を奏でる楽しさを覚えたのは事実である。
おかげで区の学校別リコーダー合奏発表会のメンバーに選ばれ、20名くらいでホールに出かけて演奏を披露した。合奏の楽しさもさることながら、なにより遠足気分が味わえ、授業に出なくて良いということが最大の喜びだった。ただ、そのよこしまな考えが災いしたのか、指揮者の真正面で演奏していた僕は、どの記念写真も見切れているという残念な思い出を残すことになってしまった。
指揮者といえば、クラス別合唱大会のときに「ミワくん指揮やってみない?」と先生からタクトを渡された。「歌が下手だからだよ」と友達にからかわれたけれど(自分でもそうなのかなと焦った)、「上手だからこそ指揮ができるの」と先生はちゃんと説明してくれた。
2拍子の指揮ゆえ下げて上げての繰り返しなのだが、両腕の振り方や強弱、全体の見渡し方やまとめ方などわりと細かく指導された記憶がある。
もちろん歌うのも好きで、音楽の授業に限らず、朝の会のときもお腹から声を出すようにしていた。僕は5年生の頃には声変わりが始まって、親や先生に無理して大きな声を出さないようにと言われていたが、「なんだか高い音が出しづらいな」という苛立ちをそのまま歌にぶつけてしまった。
中学に入ると男子はかっこつけて歌わなくなるものだが、女子とのハーモニーが心地よくてますます真剣に歌うようになった(結果的に裏声が出ない声帯になってしまったようだ……)。
そうした懐かしい記憶を呼び覚ましてくれるところが良いのだろうか。子どもたちが届けてくれるメロディーを毎朝楽しみにしている。通りしなに少しだけというところが心をくすぐる理由なのかもしれない。歌声が聞こえない日はやはり寂しい。
でも理由はそれだけではないような気もする―――。
遡ること二十数年前。僕は英語の教師になろうと思って大学で教職課程を取っており、その総仕上げとして教育実習があった。6月くらいだっただろうか。2~3週間、母校の中学で教壇に立ち、授業だけでなく教室に籍を置いて生徒の指導に当たるのだ。
通常は指導してくれる先生が受け持つ学年のみなのだが、あろうことか全学年を経験させていただくという温かい(?)施しを受けることになってしまった。教科書3冊に目を通さなくてはならず、学年ごとに教え方や生徒との関わり方も変えなければいけない。
毎日、授業をどのように進めるか、導入からまとめまで時間をどう割り振るかについての「授業案」を書き上げてチェックしてもらい(もちろん書き直しさせられた)、帰宅後も資料や小テストを作らなければならず、寝不足と緊張で文字通りへとへとになった。
大学で模擬授業をしたくらいの経験でリアルな教育の現場に身を置くのだから、覚悟していたとはいえ、さすがに想定外の全学年受け持ちはきつかった。
そんな過酷な毎日をなんとかやり過ごし、いよいよ実習期間が終わりに近づいたときのこと。体育館で学年集会があり、隅っこに立って生徒を見守るだけという束の間の休息気分を味わえる時間があった。
開け放した扉から午後の光が差し込んで床に反射し、整列して体育座りをしている1年生たちの姿を明るく照らしていた。
あくびをかみ殺している先生を目撃してにんまりし、体育館のにおいはどうしてどこも同じなんだろうとか、生徒たちの白いシャツが初々しいな、などとぼんやり考えたりしていた。
しばらくすると「起立」の号令で全生徒が立ち上がり、ピアノの音に次いで合唱が始まった。かつてこの場所で自分も歌った曲だ。歌声は体育館のドーム状の天井に反響し、一つの透き通ったかたまりとなって、どこかに羽ばたこうとしているように思えた。
おそらく真剣に歌っている生徒もいれば、いやいや歌っている生徒もいるだろう。小声でそれらしく歌っている生徒も、口パクの生徒もいたに違いない。けれど、そうしたありのままの歌声に耳を澄ますと、心がみがかれていくような感じがした。
合唱の声は、こんなに無垢で美しいものだったのか。
僕は一緒になってその旋律を胸のうちでたどっていた。歌の羽ばたきの行方を見定めようと、いや、むしろその翼に自分も乗り込みたいとの思いで顔を上げると、体育館のギャラリーのところに並ぶ窓が視界を覆いつくした。大きな窓一面すべて光に満ちている。歌はまさに最大の盛り上がり箇所にさしかかっていた。
そうだ、僕は今イノセンスの具現を目の当たりにしているんだ!
ところが、である。感動に打ち震えているのとは別の身震いが突然全身に襲いかかった。そしてその理由が何かわかったとき、歌声は遠のき、思わず涙がこぼれそうになってしまった。
教育実習生とはいえ、教師も生徒も自分を「先生」と呼ぶ。学生ではあるものの、そこでは一教師としての自覚を持ち大人の振る舞いをしなくてはいけない。当たりまえながら自分はもう生徒ではないのだ、それは遠く離れてしまったのだ。
ひしひしと感じ取ったその喪失感は思いのほか僕を揺さぶった。無垢なものに触れる喜びを感じることはつまり、自分がそうでなくなってしまった証しなのだ。
年月が過ぎ、今では教育実習のときの倍の年齢になって、音楽室から漏れ聞こえてくる歌についてこうして文章を書き綴っている。
もし、あのまま教師の道に進むなり、結婚して子どもを持つなりしていれば、道すがらの歌声に新鮮味を感じることなどなかったに違いない。
なぜ通りしなの歌声に引かれるのか。
おそらく、あの体育館でイノセンスの消滅を知って動揺した感受性さえも忘れ去り、社会の中でいかに賢く立ち回るのかを覚え、自身の心地よい世界にばかり浸かっている我が身を揺り動かす必要があったからではないだろうか。記憶の奥底に沈んだ、もう手の届かない僕自身の影が、その子どもたちの歌声に乗っかって、今一度呼びかけたのではないだろうか。
合唱、ハーモニーを忘れてはいけないよと。つまりは他者とのつながり、わかちあいである。
小学校を後にして、しばらくすると駅前の商店街に出る。朝の光が舗装された道に反射してまぶしい。シャッターを半開きの状態にして店の前を箒で掃いたり、ショーウィンドウにモップやワイパーをかけたり、幟を差すための水の入ったタンクを重たげに運んだりする様子が目に入る。行き交う人たちが足音を立てて、少しずつ街の目覚めをつくりあげていく。
駅を変えることで景色も気分も変わる。出会う何かも変わってくる。新たな発見を呼び覚ましてくれたのは、道筋の変更が実のところ無意識のレベルで生き方そのものにリンクしているからではないのか。そんなことを思いながら今日も玄関の扉を開けて出る。
※写真をJ.D.サリンジャーの『ライ麦畑でつかまえて』にしたのは、「イノセント」という言葉を見聞きするたび、この本を思い出すから。ゼミに入ると、サリンジャーを卒業論文のテーマにしようとしてあれこれ読んでいた。だからこそ体育館の動揺につながったのかもしれない。
〈出版の窓〉
ピアノ教室(音楽教室)というと、最近ではJASRACの騒動が思い浮かぶ。文字媒体でも歌詞の引用は著作権に関わるので、編集や校正をするうえで今まで以上に意識的にならざるを得ない。とはいえ、誰もが知っている歌詞ならまだしも、出典を明記せず、カギでくくることもせずに地の文に溶け込むようなかたちで著者が書き記した場合は、歌詞と気づかず出版の運びとなってしまうこともある。現に、ある日突然JASRACから申請漏れを指摘されてびっくりした、という話を編集者から聞く。
出版業界の人間も著作権に関わる当事者である以上、故意に申請漏れを目論むことはないはずだ。ウェブのコメントなど、感情的にJASRACを批判する声も多いが、著作権を守るうえでの功績は大きい。
JASRACは徴収の正当性を法的に打ち出すスタンスを少し控え、著作権使用料の分配がいかに未来の音楽市場の発展につながるか、新たな側面から考えてみる必要もあるのではないか。例えば、出版業界向けに管理している歌詞の有無や申請の要不要を全文検索でチェックできるフリーソフトを開発提供するとか。スムーズかつ安心して編集・校正作業ができるうえ、しっかりと使用料を支払える。そんなことを思ってみたりする。
《著者プロフィール》
三輪しののい
1976年生まれ。神奈川県出身。